研究室インタビュー

古い建物を今の風景に残すための構造的研究
金沢工業大学
|佐藤弘美研究室
講師
今年度で5年目を迎える佐藤弘美研究室は、「歴史的建造物やまちなみの特徴を生かしながら安全に活用するために、地震被害の分析や構造解析によるシミュレーションなどを通してそれらの構造性能について研究」している。構造系研究のアプローチ方法はさまざまだが、佐藤講師は「モノがあってこそ。できるだけ実際の建物調査に基づいて構造を評価することを大事にしている」という。調査の後に、模型を使った実験や、解析を行うこともあるが、まずは現存する建物が研究の対象となる。

講師
(さとう ひろみ)
2003年 東京都立大学工学部建築学科卒業。
2005年 同大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了。
2007年 日本学術振興会特別研究員。
2008年 首都大学東京大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。
2008年 徳島大学 ソシオテクノサイエンス研究部助教。
2012年 東京大学生産技術研究所助教。2017年金沢工業大学講師。
まちなみを意識した構造評価
近年、佐藤研究室が力をいれているのが、連棟の町家の構造性能に関する研究だ。日本の古い民家形式である町家は、まちなみに沿って2棟3棟と横に繋がっていることが多い。その構造的な効果を明らかにできれば、耐震補強やまちなみの保全に役立つのではないかと佐藤講師は考えている。現在、金沢市の東山周辺や高岡市で、連棟の町家を対象とした調査が進行中だ。調査では、最初に構造要素を記録する。柱、梁などの構造部材を詳細にみて、建物がどのように繋がっているのか(いないのか)を調べる。痕跡なども丹念に調べ、接合部が見えない場合は、その地域に残る古い建物の修理工事報告書などを参考にする。構造を把握した後、詳細な解析モデルを作成して検証したり、1/10程度の構造模型を作成し、構造実験室にて振動実験を行う場合もある。佐藤講師によれば、町家の連棟の繋がり方にはいくつかのパターンがあり、今後各地の調査を通して繋がり方と構造的効果の関係を明らかにしていきたいとのことだ。

ドローンを用いた写真測量
合掌造りの農家で有名な五箇山では、ドローンを用いて建物情報を得る試みも行っている。ドローンで撮影した複数の画像から、建物の3次元データを作成する。建物の内部や計測が難しい箇所の測量が簡便に行えるようになれば、構造評価にも繋げられると佐藤講師は期待する。今後は、3次元データを建築CADに落とし込み、構造解析モデルへの変換に取り組むとのことだ。このほか、地元石川県の古刹那谷寺で、「懸造」とよばれる建造物の構造評価に取り組んだり、2016年の熊本地震で被災した連棟町家を対象に、連棟効果の模型実験を行ったりしている。将来的には、木材の新しい活用方法などを提案することで、地元林業の活性化にも貢献したいそうだ。


建築は、意匠だけでも構造だけでも成り立たない
現在学生は8名。人海戦術が求められる現地調査などはできるだけ全員で出向く。地震計のデータ採取やメンテナンスなどは、個々の学生が行っている。学生指導は毎週のゼミが中心で、学生が「報告・発表」する回と、佐藤講師と相談しながら「作業」を進める回に分けて時間が設けられているのが特徴的だ。報告と作業の時間を分けることで、研究の継続的な進展を促せるという。佐藤講師は、「もともと大工さんの手仕事や古い建物が好きだった」という。大学の研究室で伝統的な木造建造物を対象として、調査で各地を訪れ、古いまちなみのよさに気づいたとのことだ。単独ではなく、まちなみとして古い建物を残せるよう、構造的なアプローチを続けている。
また、難解な印象のある建築構造という学問だが、「構造は、計算だけでなく計画や材料、構法など幅広く学ぶ分野である」という。「実務においても、さまざまな構造パターンやアイデアをもち、意匠設計者が思い描いているものを実現するための提案を行う構造設計は、やりがいも楽しさもある分野だ」と佐藤講師は語る。与えられた課題をこなすだけでなく、自主的に幅広く興味をもってくれるような学生に研究室に来て欲しいということだ。




研究室メンバーに聞きました
[ 質問項目 ]
建築に興味をもったきっかけや、佐藤研究室の魅力、将来のことについてお答えいただきました。
-

井上 琢剛 いのうえ たくまさ (学部4年)
小学生の時に実家を注文住宅で建てたことがきっかけで、建築に興味を持ちました。木造の建築を詳しく知りたいと思ったので佐藤研究室に進学。喜多家の内観の写真を撮り、専用のソフトを使ってモデル化して解析しています。
-

岡田 大蔵 おかだ たいぞう (学部4年)
ものづくりが好きで、建築に興味を持ったので、建築学科に進みました。佐藤先生が研究している伝統木造建築物に興味があり、佐藤研究室に入りました。現在は撮影した写真の3Dモデルをパソコンで作成し、データ解析をしています。
-
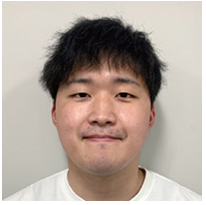
谷 篤士 たに あつし (学部4年)
建築に興味を持つきっかけとなった五重塔が幾年も地震を乗り越えてきたということもあり、木造と地震を研究している佐藤研究室を選びました。地震や常に発生している微小な振動を測定し、振動と建物の関係を研究しています。
-
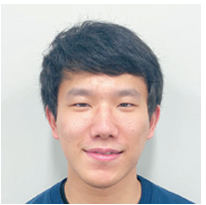
谷本 祐将 たにもと ゆうすけ (学部4年)
旅先で建物をよく目にし、建物に興味が湧きました。伝統的建造物の構造性能が、現代の建物にどのように生かされているのか、解析により明らかにしたいと思い佐藤研究室に進学。建物と地盤の揺れの関係について研究しています。
-

本間 裕也 ほんま ゆうや (学部4年)
建築学科を選んだのは、東日本大震災で被害にあった建物を見て、地震に強い建築物をつくりたいと考えたからです。現在は地震観測と常時微動測定をテーマに、歴史的建造物と地盤の揺れの関係について研究しています。
-
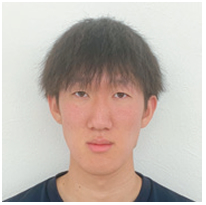
松谷 勇飛 まつたに ゆうひ (学部4年)
建築が好きで建築学科に進学しましたが、木を使った研究をしたいと思うようになり、佐藤研究室に入りました。現在は伝統構法の接合部を対象として、静加力実験を行なう研究を進めています。
-
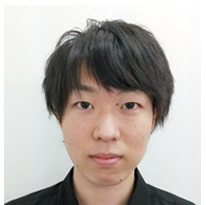
南方 優生 みなかた ゆうき(学部4年)
東日本大震災を経験し、仮設住宅をコスパよく、丈夫に建てられる地震対策がしたいと思いました。微動のデータをもとに、振動を比較することで、連続する建築物の規則性を把握し、建築物の機能を向上させる研究に取り組んでいます。
-

武藤 快依 むとう かい (学部4年)
東日本大地震を体験し、多くの人々が安心して暮らせる建物を建てたいと思いました。人々を地震から守る耐震学について学べる佐藤研究室に入りました。接合部実験を行ない、接合部の荷重変異をデータやグラフにしてまとめています。
本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。
